イメージ炉とは何ですか?
「光通信や各種レーザー機器に必要な純度の高いガラスを、無重力を利用してつくる実験がすすめられています。不純物が入るのを防ぐためなのですが、なぜ無重力を利用するのでしょうか」の「無容器溶融」は、無重力の特徴を生かした「宇宙でつくる」実験の代表例ですが、乗り越えなければならない課題が二つあります。その一つは「無容器溶融の実験では、ガラスの材料が炉の中心から動かないように、何らかの方法で材料を空中に固定する必要がありました。どのような方法でガラスの材料を空中に固定したのでしょうか。もちろんガラスの材料にふれてはいけません」の物質を空中に固定する方法(空中固定法)であり、もう一つがそれをどうやって加熱するか(加熱法)の問題です。無容器溶融のための加熱法として、「イメージ炉」と呼ばれる装置が各国で早くから開発されてきました。その原理図を下に示します。
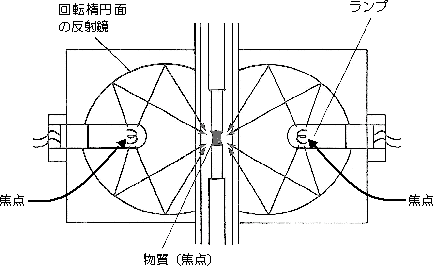
ランプをつけると、ランプから出たすべての光は鏡で反射して物質に集まり、物質の温度を1000℃以上に上げることができます。
光が物質に集まる理由は、反射鏡の形およびランプと物質の位置にあります。イメージ炉の反射鏡は楕円(だえん)形で、ランプと物質は楕円の焦点の位置にあるのです。
板に2本のクギを打ち、糸をとりつけて、下図のように糸を張った状態で鉛筆を動かしていきます。このとき描ける図形が楕円であり、クギの位置を焦点といいます。
光が物質に集まる理由は、反射鏡の形およびランプと物質の位置にあります。イメージ炉の反射鏡は楕円(だえん)形で、ランプと物質は楕円の焦点の位置にあるのです。
板に2本のクギを打ち、糸をとりつけて、下図のように糸を張った状態で鉛筆を動かしていきます。このとき描ける図形が楕円であり、クギの位置を焦点といいます。
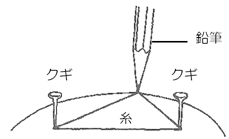
楕円にはおもしろい性質があります。「一方の焦点から出た光は、楕円の表面で反射してもう一方の焦点に集まる」という性質です。イメージ炉は、楕円を回転させた形の反射鏡を2つ組み合わせ、一方の焦点にランプを、もう一方の焦点(2つの楕円の共通の焦点)に物質を置きます。こうすれば、ランプから出た光(光も波の一種)は楕円形の鏡の表面で反射して、物質に集まるのです。
話はそれますが、放物線には、「平行な光は放物線の表面で反射して一点(焦点)に集まる」という性質があります。これを利用したのが衛星放送などを受信するパラボラアンテナです。パラボラとは、英語で放物線のことです。
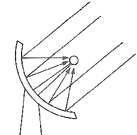
※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA



