無容器溶融の実験では、ガラスの材料が炉の中心から動かないように、何らかの方法で材料を空中に固定する必要がありました。どのような方法でガラスの材料を空中に固定したのでしょうか。もちろんガラスの材料にふれてはいけません
音波を使って固定しました。
音が空気中を伝わるときは、音源の振動にあわせて空気の濃い部分と薄い部分ができ、それらが交代で次々と発生します。空気の濃い部分を「谷」、薄い部分を「山」とすれば、音もふつうの波と同じように考えることができます。これが音波です。
「ふわっと '92」では、音波を使ってガラスの材料を空中に固定しました。原理図を右に示します。
下のスピーカー(音源)から出た音波は、上の壁で反射して戻ってきます。音波の周波数を調節すれば、下から出た波と上で反射した波が重なり、波の動きが止まった状態をつくることができるのです。
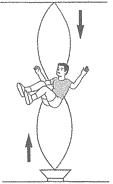
この状態で、空気の濃さの変化がもっとも小さい安定な部分に物質を置くと、物質はその位置から動かなくなります。
地上ではごく軽いものしか固定できませんが、無重力では重さがないため、ガラスの材料を空中に固定することができたのです。
ただし、温度が変わると音波の進む速さが変わるため、物質をふつうの温度で固定できる周波数と、高温で固定できる周波数とは異なります。周波数の調整のむずかしさがこの固定法の泣きどころです。
なお、空中固定法には、このほかにも次のような方法があります。
(1)物質に磁力を与え、コイルで作った磁場との反発力で固定する。
(2)物質を帯電させ、電気的反発力で固定する。
(3)気体を吹き付けて固定する。
ただし、(1)は電気を導く物質に限られます。また、(3)は温度が下がるので、加熱実験には向きません。
地上ではごく軽いものしか固定できませんが、無重力では重さがないため、ガラスの材料を空中に固定することができたのです。
ただし、温度が変わると音波の進む速さが変わるため、物質をふつうの温度で固定できる周波数と、高温で固定できる周波数とは異なります。周波数の調整のむずかしさがこの固定法の泣きどころです。
なお、空中固定法には、このほかにも次のような方法があります。
(1)物質に磁力を与え、コイルで作った磁場との反発力で固定する。
(2)物質を帯電させ、電気的反発力で固定する。
(3)気体を吹き付けて固定する。
ただし、(1)は電気を導く物質に限られます。また、(3)は温度が下がるので、加熱実験には向きません。
※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA



