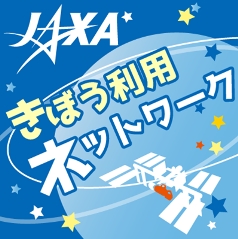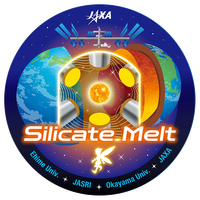
関西学院大学の河野義生教授らの静電浮遊炉※1 利用テーマ「低重合度のケイ酸塩融体における粘性、密度の温度依存性測定(Silicate Melt)※2」の成果が、Springer Nature社が刊行する国際誌Communications Earth & Environment誌に掲載されました。(論文情報)
本研究では、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟に搭載された静電浮遊炉(ELF)を用いて、ケイ酸塩マグマの密度測定に成功しました。この成果により、火星深部の核-マントル境界において、鉄に富むケイ酸塩マグマ(液体)は火星マントルの岩石(固体)よりも高密度で重力的に安定に存在しうることが示され、火星深部構造に迫る手がかりが得られました。
本成果の詳細については、大学リリースをご覧ください。
- ※1 静電浮遊炉(ELF)
- ※2 低重合度のケイ酸塩融体における粘性、密度の温度依存性測定(Silicate Melt)
研究代表者 河野 義生(関西学院大学 教授)
実験目的 地球内部のマグマの粘性変化モデルを構築するため、「きぼう」静電浮遊炉と地上での高圧実験を組み合わせ、これまで測定困難だった低重合度ケイ酸塩融体の密度と粘性の温度・圧力依存性を明らかにすることを目的としています。特に、SiO2量が少なくFeに富む低重合度ケイ酸塩融体の熱物性データを測定することで、マントル深部におけるマグマと岩石の密度逆転の可能性を判定し、地球の進化過程の理解に貢献することを目指します。
なぜ宇宙で実験するのか?
地上では、高温で溶かしたマグマが容器と反応してしまうため、火星深部構造の解明に必要な密度を正確に測るのが困難でした。しかし、ISSの静電浮遊炉を使えば、容器を使わずに2000℃以上の高温下でマグマを浮かせたまま実験できます。これにより、地上では難しい高精度な密度測定が可能になりました。
火星の深部には鉄に富む重いマグマが存在?
実験の結果、鉄を多く含むケイ酸塩マグマは、火星のマントルを構成する岩石よりも密度が高いことが分かりました。つまり、マグマの方が岩石よりも重いため、火星の深部の核とマントルの境界付近に安定して存在できると考えられます。
火星の進化に重要なヒント
このマグマは、火星ができたばかりの頃に存在していた「マグマオーシャン」が冷えて固まる過程で、深部へ沈んでいった可能性があります。これは、火星の内部構造や進化を理解する上で重要な発見です。
今後の展望
今回の研究は、これまで材料科学のために使われてきた静電浮遊炉を、地球惑星科学の研究に応用した初の試みです。今後は、実際の火星のマグマにより近い成分(Al2O3やCaOなど)を含む試料での宇宙実験や、SPring-8を利用した高圧環境での測定が進められる予定です。
学術論文
†筆頭著者;*責任著者