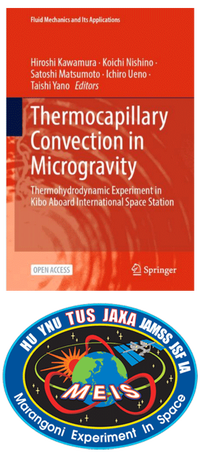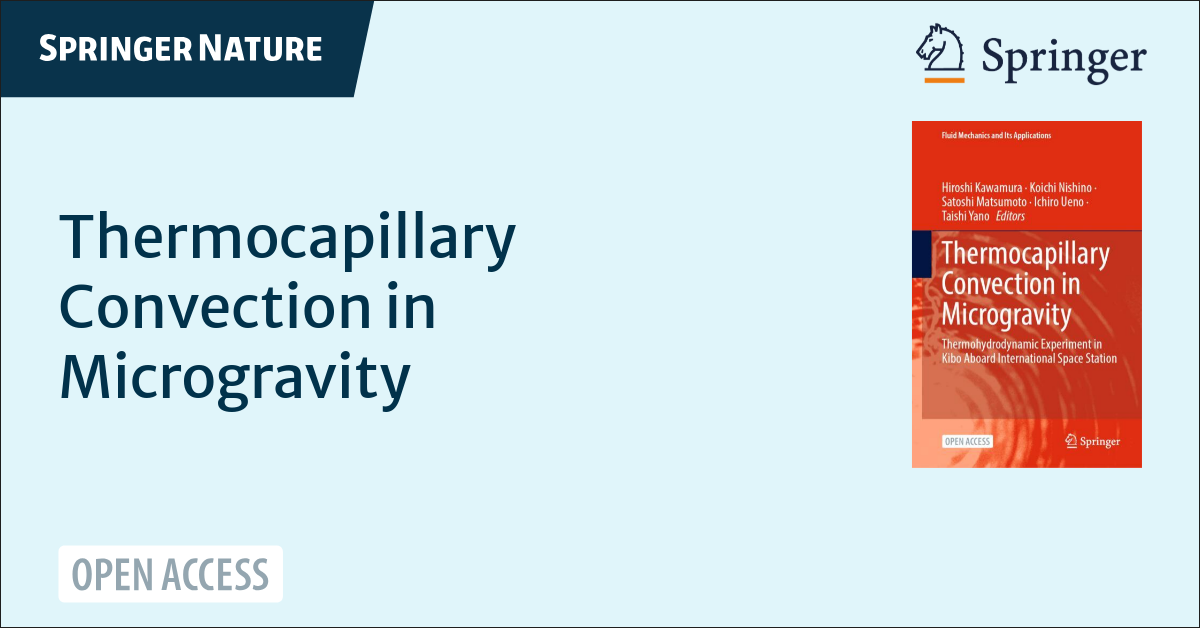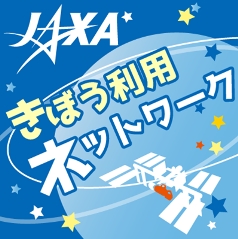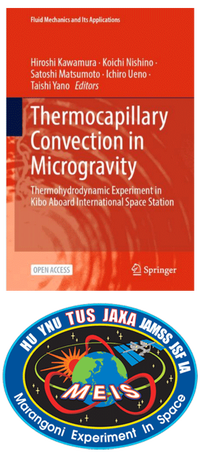
国際宇宙ステーション(ISS)・「きぼう」日本実験棟での最初の科学実験「MEIS※」についての学術書がSpringer Nature 社より出版されました。(書籍情報)
本実験は、無重力下においても発生する表面張力に起因する対流「マランゴニ対流」に関するもので、「きぼう」における実験の背景、経緯および成果を報告するものです。さらにマランゴニ対流の入門的な説明から、背景となる理論や地上での準備実験、そこから得られた成果などを系統的に解説しています。また、表面張力について、マイクロ・ナノ流体への近年の応用や、人類の宇宙活動における利用などの将来展望にも触れた396ページからなる書籍です。
世界中の多くの方々に読んでいただけるよう、書籍のPDF ファイルはオープンアクセスとしています(無料でダウンロード可能)。
※ Marangoni Experiment In Space (MEIS)
本書は、「きぼう」での実験成果を中心に、大学生やこの現象に初めてふれる方々が温度差に起因する表面張力の差により発生する「マランゴニ対流」の基礎を学べるよう、日常に現れる現象の解説から始まり、続いて理論的解析、地上および微小重力実験結果を交えながらマランゴニ対流現象を体系的に解説しています。
また、マランゴニ現象に起因するマイクロスケールでの表面張力流れなどを通して最近のマイクロ・ナノ技術への応用を紹介し、最後に将来の宇宙探査における流体ハンドリングなどへの表面張力の活用を展望しています。
以下では各章の構成を紹介します。
自然界や日常生活に現れる表面張力について紹介します。さらに、本書の主要テーマである微小重力における流体現象、ISS、そして「きぼう」についても説明します。
本書の主テーマである表面張力の発生メカニズムとその温度依存性について、巨視的な熱力学的観点と微視的な分子動力学的観点の双方から体系的に解説し、さらにそれらをより直感的にわかりやく説明します。
本書の主題であるマランゴニ対流に焦点を当てます。まず、この対流を記述する基本方程式と無次元数を示し、次に、無限幅の液体膜層と無限長の液柱という2つの代表的な形態を対象として、マランゴニ対流の不安定性について、線形安定性解析の手法と結果を解説します。
実際の半導体製造における結晶成長や、「きぼう」の軌道上実験で用いられている有限長の液体におけるマランゴニ対流について解説します。本章では、結晶成長技術におけるこの現象の関わりを概観し、まずこの分野における初期の研究の紹介から始め、次に振動流への遷移条件、モード数、粒子集合現象(PAS)といった重要な現象について解説します。
これらの知見の多くは、軌道上実験の準備過程において実施された一連の実験や数値解析から得られたものです。さらに、液柱内の粒子がループ形状に集合する現象(PAS)について、その発生原因を考察し、マイクロ・ナノ技術への応用についても解説します。
遷移条件に影響を与える重要な要素である、周囲気体との熱交換の実質的な影響に焦点を移して、振動流への遷移を制御または抑制する方法について実験結果を示し、考察します。さらに、実際の結晶成長により近い体系(液柱の両端を低温にして中心付近を高温に保つ「フルゾーン体系」)についても実験の結果を紹介します。
本書の主眼である、「きぼう」内で実施された実験について詳述します。実験装置、条件、方法に加え、マランゴニ対流実験で活用したユニークな計測技術についても解説します。本章では、振動流への遷移条件、速度場と温度場の時空間構造、自由表面を介した熱交換の影響、マランゴニ対流とISSにおける残留重力加速度(すなわちgジッター)による液柱の動的挙動、そしてカオス状態または乱流状態への遷移過程についても取り上げています。
主に「液柱」とよばれる系を対象として、マランゴニ効果(熱毛細管効果)によって駆動されるいくつかの特異な現象について述べています。まず、液柱形状において発現することが知られている、いわゆるHydrothermal Wave不安定性において、小さな粒子によって形成されるコヒーレント構造が観察されていることについて、地上および微小重力実験で得られた知見を紹介します。また、液柱の伸長に伴う破断(ピンチオフ)に注目し、微小重力実験および数値解析における検証、さらに、マイクロ流体工学における実用例として、ピンチオフ後に残留する液滴の体積制御について紹介します。
液滴や薄膜などの様々な系に関する研究成果を、特にマイクロ流体力学に焦点を当てて紹介します。前章で取り上げた液柱とは異なる系での微粒子の挙動について、地上および微小重力下での実験を通じて得られた知見を説明します。また、表面張力の不均一分布が、コーティングや熱交換といった基板プロセスにおいても重要な役割を担うことを示し、溶媒の蒸発によって引き起こされる濃度差駆動マランゴニ効果についても考察します。さらに、表面張力が有するユニークな特性の一つとして、表面張力の温度依存性の符号が温度帯によって逆転する特異な性質を持つ水溶液に注目し、熱交換器における熱伝達特性の向上への応用について、実験結果を交えて解説します。
ISSと「きぼう」の歴史、現状、そして将来計画について概説します。さらに、人類の月への再訪や火星探査といった将来の目標にも触れ、とくに本章では、その中での表面張力に関わる現象の重要性と、それを活用するための積極的な開発の現状および将来展望について考察します。
いま宇宙探査は新たな段階を迎えていて、その重点は月や火星へと焦点が移りつつあります。微小重力から月面の1/6G、火星の1/3Gまで、さまざまな重力環境での液体ハンドリング技術が不可欠となります。このとき、本書であつかってきた毛細管力(表面張力)、熱毛細管力(温度分布に起因)、そして溶質毛細管力(濃度分布に起因)を最大限に活用することで、最小限の外部エネルギーで動作することのできる受動(自発型)ポンプが実現することを紹介します。